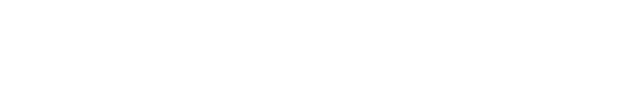認知症と歯科医療について
歯科医師 亀澤亜季
先日千葉市より、高齢者を診療する機会の多い歯科医師向けに、認知症患者とその家族を支えるための必要な基本知識を確認し、認知症への支援体制構築の担い手となることを目的とした研修会が開催されました。
超高齢社会である現代、自分や家族のためにも確認しておいた方がいい知識だと考え、研修会の内容をまとめてみました。
高齢者の口腔機能と認知症:これからの歯科医療のあり方
高齢化社会が進む中、私たちは単に歯の治療を行うだけでなく、患者さんが「自分らしく生きる」ための支援を提供することが求められています。
口腔機能―食べる、話す、呼吸する―は、個人のアイデンティティの実現に直結しており、その維持は高齢者のQOL(生活の質)向上に不可欠です。
高齢者に多くみられる嚥下障害
高齢者における嚥下障害は、単なる「老化」の一部ではありません。
フレイルやサルコペニアといった身体機能の低下、さらには顎椎の変性や口腔内の環境変化(歯の欠損、ドライマウス、口腔がんなど)が複合的に関与します。
また、脳血管障害や神経筋疾患、認知症など全身性の病態が隠れていることもあり、家庭環境や食事内容が個人差に大きく影響します。
こうした背景を理解することで、早期発見と個別対応が可能となり、全身状態の改善につながります。
多様な認知症とその摂食・口腔への影響
認知症は大きくアルツハイマー型、脳血管性、レビー小体型の三大認知症に分類され、さらに前頭側頭型認知症も注目されています。
アルツハイマー型認知症
全認知症患者の約60%を占め、脳内でアミロイドβ蛋白やリン酸化タウ蛋白が蓄積し、海馬の萎縮から物忘れや高次脳機能の低下が現れます。
初期は嗅覚障害や食品パックの扱いの困難さ、進行に伴い介助が必要な摂食障害へと発展します。
歯科医師は、発症後のおおよその寿命(約10年)を踏まえた治療計画を立てる必要があります。
脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血などの後遺症が原因で、発作ごとに症状が階段状に進行します。
記憶障害が必ずしも現れず、感情のコントロールが難しいことも。麻痺の影響が摂食に影響するため、口腔清掃などのケアには片麻痺への配慮が求められます。
レビー小体型認知症
脳幹や大脳皮質にレビー小体が出現し、記憶や視覚情報の処理機能に障害が現れます。
幻視やせん妄、さらにはパーキンソン症状が見られるため、オーラルディスキネジアによる口腔内の違和感や、幻覚による摂食拒否などが問題となります。
前頭側頭型認知症(ピック病)
若年発症の例も多く、初期から性格変化や社交性の消失、判断・実行機能の低下が目立ちます。
食事中のマナーの乱れや早食いなども見られ、従来の認知症とは一線を画した対応が求められます。
歯科医師としての新たな挑戦
これからの社会において、歯科医療者は単なる治療者ではなく、患者さんの生活全体を支えるパートナーとしての役割が期待されます。
健全な口腔環境の整備は、認知症予防にも寄与するとされ、歯10本以上が維持されることで認知症リスクが軽減されるという報告もあります。適切な咬合の保持や、噛める義歯の作成は、患者さんの「食べる喜び」を守るための重要な施策です。
また、摂食・嚥下機能の早期発見と治療は、脳機能全体に関わる問題であり、介護状態に入る前から継続的なケアが求められます。
患者さん本人はもちろん、家族や介護者とよく対話し、本人の意向や希望を尊重した治療計画を策定することが、最期まで質の高い生活を実現する鍵となります。
患者さんができることを少しづつ増やしていくという、成功体験を積み重ね、場合によっては治療からの撤退を検討することも必要になります。
結びに
高齢者の嚥下障害や認知症は、多面的な問題を内包していますが、その背景には「食べる喜び」や「自分らしく生きる」という根源的な人間性が存在します。
歯科医師は、口腔機能の維持を通して患者さんの生涯にわたるQOL向上をサポートする重要な存在であると同時に、エンドオブライフケアのパートナーとしての役割を果たすべきです。
今後も、患者さん一人ひとりの声に耳を傾け、専門的かつ温かい支援を提供していくことを心がけようと思います。